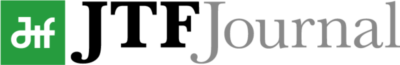自動翻訳時代を生き抜くための日本語原稿の品質管理(後編)
講演者:ヤマハ株式会社 音響事業本部 基盤技術開発部 製品情報デザイングループ リーダー 石川 秀明さん
●翻訳しやすい日本語原稿を作るための教育訓練
次は、このような翻訳しやすい日本語原稿を作るための工夫についてお話します。まず、次のような私たちメンバーの教育訓練が軸になっています。
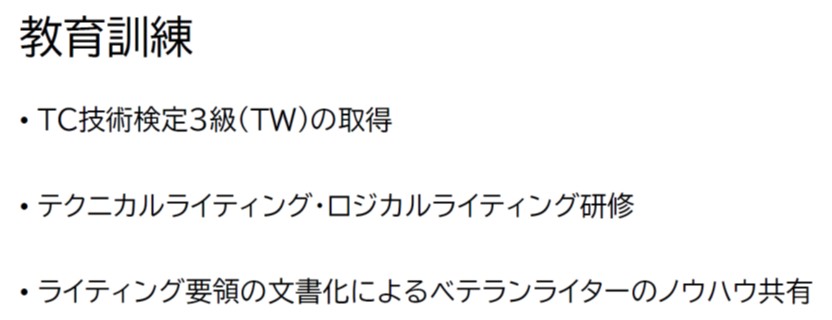
私たちの部門では、先ほど(前編)の自己紹介でお話した日本テクニカルコミュニケーター協会が主催しているTC技術検定3級を、配属後に必須で取得してもらっています。これをやることで、基本的な日本語の書き方、日本語の文法、用語の使い方をマスターすることができるので、配属された初年度の研修期間の中で、TC技術検定3級を取得するための勉強も合わせてやっていただいています。
ヤマハには、マニュアルを作るときのスタイルを決めるスタイルガイドがあります。そういったところも、TC技術検定3級の教科書になっている『日本語スタイルガイド』の中にほとんど網羅されていますので、我々のスタイルのルールを学ぶ内容にもなります。そのためにも、このTC技術検定3級を取っていただいて、まずは正しい日本語をマスターもしくは復習して、より正しく理解したうえで、日本語を書いてもらうというアプローチをしています。
それから、テクニカルライティングやロジカルライティングの研修があります。これは内部外部を問わず積極的に受けていただいています。特にロジカルライティングは、日本語だけでなく、英文の研修も合わせてあります。その両方を受けることで、日本語と英語の違いや英語のロジカルライティングの特徴などを理解し、翻訳しやすい日本語の書き方をするにはどうしたらよいかを考える教育訓練になります。
今のヤマハの新入社員研修でも、このテクニカルライティング研修は全員が必ずやるようになっています。議事録の書き方やEメールの書き方などでも、主体が誰なのか、主語が誰なのかをはっきりさせる。例えばEメールでしたら、誰か他の人に動いてもらわなければいけない仕事を依頼するときなどに、「誰がいつまでに何をやるのか」をはっきりさせる、そうした書き方が自然と身に付くという効果を期待しています。
テクニカルライティングやロジカルライティングの研修は新入社員だけでなく、経験のあるメンバーも節目節目でやっています。
さらに、ライティングをするときのコツやノウハウをまとめた「ライティング要領書」というものも作っています。いわゆるプロセスや会社の仕組みについては、ISO9001にのっとって、すべての仕事において手順書などが存在しますが、その手順書で表現できない、例えば原稿を書くときの考え方などは、ベテランライターのノウハウをふんだんに取り入れた「ライティング要領書」として文書化しています。
これを、配属されたばかりのときなどに、まずは研修という形で受けます。そして経験を重ねた後、今度は教える側になってライティング要領について考える。またその途中でも、ライティング要領書自体を通常の手順書と同じように改訂し、新しい情報にアップデートしたりする中で中身を検討していきます。こういった形でライティングのノウハウについても明確に文書化し、共有するようにしています。
このような地道な小さな訓練をジャブのように繰り返して、日々レベルアップし、文章に対する感性を高めていくアプローチをしています。
●プロセスの構築
プロセスのほうでも工夫をしている部分があります。
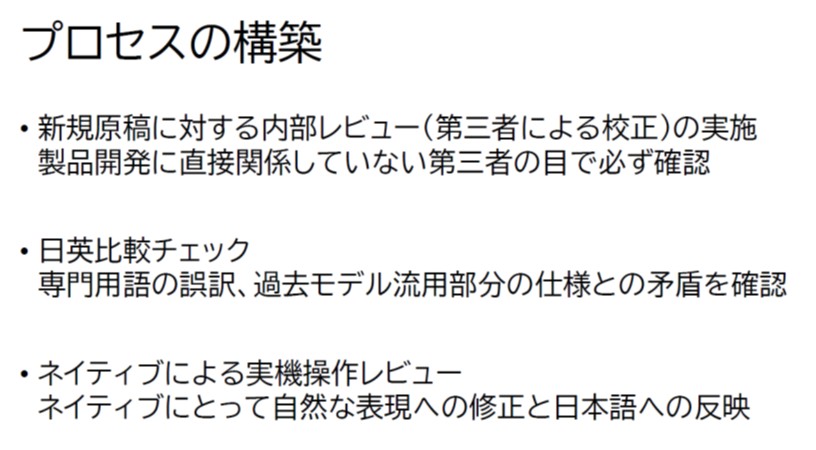
まず、新規原稿に対する内部レビュー、いわゆる第三者による校正を実施しています。対象となっているマニュアルの製品開発に直接関係していないメンバーが、第三者の目でその文章を見て、わかりやすいかどうかを確認します。これは、その文章自体をアップデートする意味もありますが、第三者の目で見て、自分が見えていない視野を獲得する。それから、レビューをする側も他人の文章を読むことで、良い文章、悪い文章に出合いますので、経験値になっていきます。
実は、ここを自動化できないかと検討したことがあります。AIの力や何かツールを使ってできるんじゃないかと考えましたが、検討している中で、第三者による内部レビューが教育訓練の面で非常に大きな貢献をしているということがわかりました。
そこで、ここの自動化は諦めて、今は教育訓練の一環として人の手でやっています。そうすることで、たくさんの文章に触れる機会もありますし、やはりたくさん良いものを見る、それからチェックをするという経験を繰り返すことによって、感度が良くなると感じています。
それから、日英の比較チェックです。これも非常に大切なプロセスです。英語の最初の原稿ができあがったときに、日本語とその英語のマニュアルの校正用データを両方並べて、1文ずつゆっくりとチェックします。非常に大変なんですが、非常に有効なプロセスです。
主に専門用語の、先ほどありました例えば「Chorus」とか「音質」とかいったものの誤訳のチェックや、マニュアルの場合は過去のモデルを流用して作ることが多いのですが、その流用部分の間違いが実は非常に多いです。「ここは流用しているから大丈夫だよね」と捉えてしまう。それから、翻訳メモリーが的確に当たって、「ここはあまり修正いらないよね」というような原稿の中に、実は過去モデルと新モデルの仕様の矛盾などが埋め込まれて問題になることがけっこうあります。そういったことを防ぐために、日本語と英語の原稿を必ず比較してチェックをするようにしています。
もしここで、「ここの英語表現がちょっとわかりにくいな」という部分が出てきたときは、その英語だけを直すのではなく、日本語の原稿もできるだけ直すようにしています。そうすることで、日本語もよりクリアに伝わりやすくなることが多いので、日英の比較チェックは手間もかかりますが、有効に機能しているプロセスです。
また、英文のマニュアルができたときは、翻訳会社で翻訳した場合も、ネイティブの楽器の操作ができる方に実機で、実際に操作してもらってレビューをしています。
ネイティブにとって自然な表現になっているかどうかというところと、その自然な表現で書かれたものが日本語にもフィードバックできる場合が非常に多いので、そこを合わせて確認をしてもらっています。
これも侮れないところです。やはりネイティブの方が実際に製品を操作して感じたことは、より多くの人に関わる部分が多く、「ここが足りていなかった」とか、いろいろなことが見つかりますので、実機操作したネイティブな人がどう表現するのかを拾い集めて、活かしていくアプローチを取っています。
このようにけっこう手間がかかることばかりやっているのですが、これを省略してしまうと実感のこもったマニュアルにはならないので、こういったところを大切にしています。
●スタイルガイド・用語集の整備
それから、これは当然なことですが、スタイルガイドや用語集の整備も必要です。
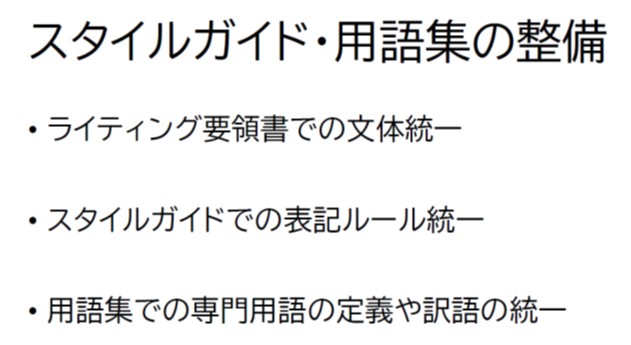
先ほどご紹介したライティング要領書で文体、スタイルガイドで表記ルール、用語集の専門用語で定義、訳語の統一などを行っています。ここはもう皆さんご存じの通りで、特に用語集などがあるのとないのとでは翻訳の効率が全く違うと思いますので、しっかりメインテナンスをしていきたいと思います。
以前、用語集に実は登録しすぎて、こんなことまで登録しているのかというような用語まで入れてしまっていたので、非常に用語が探しにくい状況になっていました。そこで今、見直しを入れて、よりすっきりした形で本当に必要な用語だけが入っている用語集を作ろうとアプローチをしているところです。まだまだやれることがたくさんあるので、我々も常に進化を目指して頑張っていきたいと思っています。
●ツールの活用
校正ツール、辞書ツールなどのツールを活用することも非常に有効です。例えば校正ツールの「Just Right!」であったり、辞書ツールですと、テクニカルコミュニケーター協会がリリースしている「日本語スタイルガイド」に合わせた辞書や、日本翻訳連盟の辞書もインストールして活用しています。それらの辞書に入っていることで、使える用語がすぐ確認できるので、非常にわかりやすいです。
昨今ではスタイルガイドや用語集をシステムの中にインプットして、そのツールでライティングをすると、「これはスタイルガイドと違う」といった指摘や、「こういった文章のほうがいいですよ」というような例示をしてくれるシステムが世の中にはあるようです。
これらも非常に有効だと思いますし、大きな企業ではけっこう採用されていると聞いていますが、ヤマハでは残念ながらまだ採用していません。費用対効果の点で手を出せずにいます。今は人間力でカバーしているところがたくさんあるのですが、ゆくゆくはそういったところをシステムの仕組みでやることで、より早く快適に仕事ができる状態を作れるといいなと考えています。諦めずにいろいろなシステムや新しい仕組みの検討などは進めていきたいと思っています。そういったアンテナを高く張っていることも重要かと思います。
●人間による翻訳は必ず残る
最後に、ソースクライアント側からのメッセージという形でお伝えしたいと思います。
まず、人間による翻訳は将来も必ず残ると私は確信しています。意思を持った判断は自動翻訳ではできませんので、意思を持った判断を伴う翻訳の部分は人間がやるしかありません。
また、文化的な背景を踏まえた、いわゆるクリエイティブ翻訳は、人間にしかできないものだと思います。新しい価値を生み出したり、付加価値のある情報を作ったりするのはおそらく人間だけだと感じています。ここは自信を持って、翻訳者の皆さんにクリエイティブな部分を担っていただきたいと期待しています。
それから、機械翻訳、自動翻訳をやったときに、ポストエディットという作業があります。ここをクリエイティブな仕事で付加価値にするのも、人間のやれるところだと思います。
翻訳者にとっては、ポストエディットは苦行のようなものなのかなというふうに想像しています。翻訳者の皆さんの持っているスキルや知識、過去の経験などをすごく安直に使っているように捉えられているんじゃないかなと感じていますが、そこを、一歩進んだクリエイティブな作業に転換するのも、おそらく人間にしかできないことだと思います。ぜひここを、皆さんの存在価値になるようなところに引き上げていただけると、より自動翻訳と共存した世界になっていくんじゃないかなと想像しています。
●言葉の置き換えではなく異文化への架け橋を
翻訳とは言いますが、我々がソースクライアントとして期待しているのは、やはりローカライズなんです。言葉の置き換えではなくて、異なる文化への架け橋を翻訳の部分が担っていると考えています。いわゆる言葉の置き換えの翻訳は、おそらく自動翻訳ですべてできてしまうんじゃないかと思いますが、異なる文化への架け橋の部分に関しては、人間の翻訳者にしかできないことだと思います。
ここは、日英も英日の翻訳も同じだと思います。その言語を使う人たちの持っている文化への馴染ませ方というところが、翻訳の中で非常に大きな力になっているのではないかと思うので、「異なる文化への架け橋なんだ」というところを、ぜひ皆さんにやっていただきたい、やっていただけると非常に嬉しいです。
●低価格よりも短納期
ちょっと本音トークになりますが、我々ソースクライアントが最も嬉しいのは、どちらかというと低価格よりも短納期です。早くできるほうが嬉しい。
例えば、自動翻訳を活用して、短納期、多分量で、しかも高品質を保てたら、価格は据え置き、あるいは特急料金ということで少し高くなっても非常に大きなメリットを感じます。
短くなった分、元のソースの言語、例えば日本語のクオリティを上げることもできるし、多言語翻訳した後の工程が圧迫されることもありません。特に工程が後ろになればなるほど日程は詰まっていくので、その中での対応に今、非常に苦労しているところです。
特に多言語展開をした後、例えば25言語に翻訳すると、25個直さなければいけなくなるところもあるのですが、そこが短い期間でできるようになるのは、我々ソースクライアントからすると非常に魅力的です。価格が下がるよりも短納期のほうが、非常に価値が高いと思います。
●クリエイティブなポストエディットが大きな武器に
そういう意味では、これから先、自動翻訳を使う場面が非常に多く出てきて、ポストエディットが非常に多くなると思います。特にマニュアルは100パーセント、ポストエディットをやることになります。例えば法令規制などを踏まえたときに、ポストエディットしない状態でマニュアルを世の中に公開することは今の状況ではできません。
ですからポストエディットの仕事はなくならないと思いますが、そこでクリエイティブなポストエディットの仕事を実現する翻訳者がいたら、将来、企業の強力なパートナーになるのではないかと思います。ここは翻訳者の方にはなかなか受け入れがたいところかもしれませんが、ポストエディットの部分は今後ますます重要な位置付けになってくると思いますので、ソースクライアントとしては、ぜひ意識の中に置いておいていただけると嬉しいです。
これから先も自動翻訳はますます進化していくと思いますし、既に自動翻訳と共存をしていくしかない状態になっています。そうした中で、翻訳者の皆さんがよりクリエイティブな状況になっていけるように、ソースクライアントとしてできるだけ品質の高い日本語を提供できるように、これからも努力していきます。
皆さんと協力して、よりよい情報を世界に発信していきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。講演は以上になります。ありがとうございました。
◎講演者プロフィール

石川秀明(いしかわ ひであき)
ヤマハ株式会社 音響事業本部 基盤技術開発部 製品情報デザイングループ リーダー
1997年ヤマハ株式会社に入社。小売店での販売、ユーザーサポート、国内海外マーケティングを経て、2008年よりマニュアル制作を担当。入社以来、一貫して「顧客接点」での業務を手掛けており、その経験を活かした製品情報のデザインによる顧客体験価値の創出に日々尽力している。